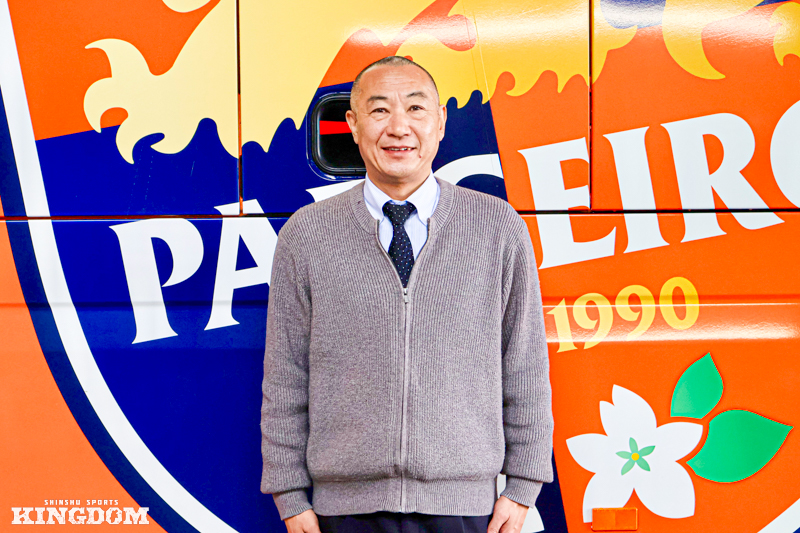長野GaRons
酒井 駿

2024年9月、酒井駿が3シーズンぶりに舞い戻った。かつて長野GaRonsを力強く牽引した、地元出身のアウトサイドヒッターだ。旧V1のヴォレアス北海道に在籍した23-24シーズン限りで引退を発表したものの、翻意して現役続行。何を思って戻ってきたのか、価値観の源流はどこにあるのか――。涼しげな表情の裏に潜む、不屈のスピリットに触れた。
文:原田 寛子/編集:大枝 令
KINGDOM パートナー
現役引退を翻意して故郷に帰還
北海道の3年間で得てきたものは
本来いるはずのない人間が、そこにいた。
2024年6月16日、小諸市総合体育館。
国民スポーツ大会県予選の会場に、長野ガロンズのユニフォームを身にまとった酒井駿の姿があった。2021-22シーズンからはヴォレアス北海道に在籍し、V1でのプレーも経験。今年4月には現役引退を表明していた。
SNSではファンがにわかにざわついた。
「酒井選手がガロンズ?ふるさと枠?」
「しゅんしゅん、帰っておいでよー」
そんな声が巻き起こるほど、ガロンズにとっては象徴的なプレーヤーと言えた。コート外では穏やかな笑みをたたえるが、ひとたびコートに入ると豹変。強烈なエネルギーでチームを牽引する。在籍2年目の2020-21シーズンは主将も務めた。

プレーの面でもそれは同様だ。身長182cmと目立ったサイズはないものの、レシーブの安定感を兼備する巧打のアウトサイドヒッター。トスが乱れると、むしろ目が輝く。セッター出身だから、上げる側の機微もわかる。
「普通のトスは普通に打てて当たり前だけれど、いかに困った状態を打破するか。そういう部分に生きがいを持っていると思う」
篠崎寛監督はそう評する。
そんな酒井が、ガロンズに帰ってきた。
2021年、V2参入3シーズン目。
ガロンズは10勝10敗の6位と過去最高の成績を収めたものの、経営面からV2ライセンスの条件を満たさずV3降格。酒井は苦渋の決断を下した。
「『強くなりたい』という気持ちがまさっていた。続けるからには勝ちたいし、自分を向上させたい。一生の中でチャレンジできるタイミングは、年齢的にも今しかないと思った」
突き動かしたのは強さへの渇望、ただそれだけ。篠崎監督との話し合いを重ねる。主将としてチームを率いていた酒井が抜けるのは手痛い。だが最終的には本人の意志を尊重し、北の大地へ酒井を送り出した。
「いずれはガロンズのために何かできれば」
そんな思いを芽生えさせながら、新天地に活躍の場を求めた。
ヴォレアス北海道は、旭川市を拠点とする新進気鋭のクラブ。学びは多かった。チームの教え、選手が持つ意識、仕事とバレーの関係性。まず選手は「株式会社ヴォレアス」に在籍し、チームの運営会社で業務に従事する。営業担当だった酒井は、自らチームのスポンサー契約を取りに道内を東奔西走した。

「僕らが頑張るので応援してください、と頭を下げる。帰属する企業がない分、より地域に根差したチーム作りをして、たくさんの企業から応援してもらわなければいけない。『選手が来てくれた』と言われることもあった。断りづらいと思う企業も多かったと思うけど」
そうして支援の輪を広げた。
試合にも企業からたくさんの応援が駆けつけた。
23-24シーズンには“四度目の正直”を乗り越えてV1参戦。初めて国内最高峰のトップリーグに身を置いて、衝撃を受けた。
選手個々のポテンシャル。
組織としての洗練度。
そもそもの力量の格差――。
どれだけ高く跳んで打つスパイクも、高身長の外国籍選手が跳んだブロックに軽々と阻まれる。どうしようもない差に挫折を覚えた。
「以前は(V1の)VC長野(トライデンツ)が勝てないのを見ていて『なんでだろう』って思ったこともあったけど、その理由が身に染みて分かった」
それでも全く通用しないわけではない。いかにブロックをかわしてスパイクを打つか。試練に直面した時に向き合う突破への模索は、苦労と同時に楽しみもあった。
ケガに悩みもがきながら戦った時期もある。
在籍3シーズンが経過し、現役に区切りをつける意向は固まっていた。
――はずだった。
酒井のもとに、一本の電話が鳴る。
「ガロンズに戻ってきてほしい」
篠崎監督からだった。
胸中には確かに、「ガロンズへの恩返し」という思いがある。その時が来たのかもしれない、と感じた。結婚して父親になったこともあり、帰郷を決断。北海道で積んだ営業の経験もあるし、サポートとして戦略や運営面で力になりたい。そんな思いを伝えたが、返事は予想外のものだった。
「どうせやるなら選手で」
そう言われても家庭環境は以前と違う。従来のような練習を続けることはなかなか難しい。選手生活を終える心は決まっていたはずだった。

しかし酒井は知っていた。
篠崎監督は、自分が折れるまで粘り倒すタイプだということを。
翻意する未来はおそらく、予見できた。
そもそも、心の片隅にくすぶっている炎も確かにあった。それは北海道を去る時に感じていた、自分に対する成長の余地。絶対的な高さにはかなわないという挫折の裏で「高さでかなわないなら、それ以外で決めればいい」という思いもあった。
まだまだ自分は成長できる。
負けは学びの宝庫でもある。「失敗」ではない。
KINGDOM パートナー
負けを負けで終わらせはしない
幼少期に練り上げられた「哲学」
バレーボール好きの両親と、一足先にチームに入っていた弟の影響から、小学校3年生で弟と同じ若穂ジュニアに加入。三水ジュニアや小布施などと一緒に県内上位常連に名を連ね、優勝を目指して練習を重ねていた。
ここでバレー人生の核が形成されていく。
「練習すれば強くなれる」
「やってきたことは結果に結び付く」
練習のつらさから「行きたくない」と両親に訴えたのは一度だけ。「自分で決めたことを一貫して続けなさい」という言葉で奮起し、厳しい練習も乗り越えてきた。「今まで続けていられるのも、この言葉があったから」と回顧する。

そして転機の中学校時代を迎える。
裾花中だ。
言わずと知れた女子バレーの全国的な強豪校。
全国中学大会を制覇すること6回。日本代表・石川真佑をはじめトップリーグの選手も数多く輩出している。
ただし、男子は日陰の存在だった。
練習時間として与えられた時間以外には、体育館を使えない。自主的に「土日に練習がしたい」と訴えても使えるのは1〜2時間。すぐにネットは女子用に高さが変わる。そもそも入部当時の男子は「上を目指す集団」ではなかった。
「若穂ジュニアで長野県の1〜2を争っていたところから、地区大会までしか行かれないことに納得がいかなかった。やるからには勝ちたいし、強くなりたい。中学1年生の頃はその準備をしていた」
幸い、顧問の新任教師はバレー経験者だった。加えて自分とは別のジュニアチームでプレーしてきたチームメイトと環境を作ろうと動き始めた。
まずは部員を集める。試合ができる人数が集まらなければゲームができない。積極的に友人を勧誘した。もともと表に出て目立つタイプではなく、どちらかと言えば内向的。それでも「強いチームにしたい」という思いが酒井を動かした。
野球部や帰宅部などの友人を勧誘。「半分だましたようなもの」と笑うが、同級生の部員は7人まで集まった。

バレーボール未経験者もいる中で、自身はジュニア時代のオポジットからセッターへ転向。専門的な教えを受けられる環境はなく、すべて独学だった。難しさを感じながら模索する日々が続く。
その一方で実戦形式の練習を重ねるべく、顧問に頼み込んで練習試合を組んでもらう。ここでも当然簡単に勝てるわけがない。悔しい思いが重なった。
「選手同士で自然と『勝つためには次どうしたらいいか』という会話ができていた。自分たちには何が足りないか、何がいけなかったか。やる気を失いそうな部員もいたけれど、同じ熱量に持ち上げられるように自分から意識をして話したこともあった。でも何より、全員が『強くなりたい』というベクトルに向かっていたのは大きかった」
一つ負けるごとに弱点を強化して、強くなる。
それをひたすら繰り返してきた。
たとえ負けても、次に勝てば失敗ではない。
その繰り返しで、男子バレー部の快進撃が始まる。
2年になると、それまで以上にメンバーも顧問も練習に熱が入った。厳しい指導も加わり、チームは少しずつうまく回り始める。変わらないことは、負けた後の反省と課題克服というルーチン。その結果は徐々に現れる。「負けるたびに強くなる」ことを、部員たちは肌で感じていた。
この年は長野県中学総体でベスト8。大きくジャンプアップした。

そして迎えた3年生。後輩たちにも「強くなりたい」という思いは伝わり、より成熟したチームとなっていく。一つずつ勝利を重ね、入学時に地区大会どまりだったチームは全国中学大会ベスト8まで躍進した。
「バレー人生の中で中学時代が一番面白かった」
酒井は半生を振り返り、そう断言する。部員集めに始まり、練習方法の模索、意識の共有――。もちろん監督の指導もあったが、自主的に働きかけ、前向きに引っ張ることで組織が変わる経験を得た。
負けを負けのままで終わらせない。
その思考が確立された。
大学4年でアウトサイドヒッター
セッターの心理も理解してプレー
高校は京都の強豪・東山へ進学。若穂ジュニアと同じように、東山でもレシーブに重きを置く練習スタイルが取られていた。「ボールを落とさなければ負けない」「ひたすら拾う」という泥くさい練習は肌に合っていた。さらに180cm近くまで伸びた身長を生かし、ブロックも得意なセッターとして存在感を示していた。
1〜2年時は春高1回戦敗退。3年時は主将を務めながらも春高に出場することはかなわなかった。中学で経験した「全国」とはレベルが違う難しさを痛感した。

専修大に進学すると、さらなる壁にぶつかる。
為我井太也(元トヨタモビリティ東京スパークル)が正セッター。試合に出る機会は限られる。さらに監督からはアウトサイドヒッターのポジションでスパイクを打つ練習も課されていた。岐路に立っていた。
「4年生になった時には『試合に出たい』という思いが強かった。スパイク練習もかなり重ねていたし、セッターを固執するよりもアウトサイドヒッターにコンバートする方が試合に出られるかもしれないと思った」
一念発起。
実際にコンバートしてみると、点を取ることの難しさを体感した。だが自分はセッター経験者。試行錯誤しながら9年間続けてきたポジションだっただけに、アウトサイドヒッターでもその経験は大いに生かされていた。
「この一本で決めてほしい」
セッターはそう願ってトスを出す。
「打ちやすいポイントに上げてほしい」
スパイカーはそう願って跳ぶ。
しかしコントロールがずれた時、焦る。
セッターの心理はよくわかるし、それならば自分のところで吸収すれば物事はスムーズに回る。打てるレンジを広くすればいい。
酒井はそう考えた。

それには、さらなるスキルアップが必要だった。さまざまな打点を試してうまくブロックをかわす技術を磨き、2段トスが上がった状況でも相手がいないエリアを見つける視野の広さも身につけた。特に初期は、同じポジションだった弟のフォームを参考にもしていた。
それは思い通りにスパイクが打てずに負けた試合から身に付けてきた。「負け」で終わらせずに自分の糧にすること。いつしか、トスが難しいほど、打ち切るのが面白くなっていた。
――負けからの学びは宝物。失敗にはしない。
就職の予定が1本の電話から急転
新生Vリーグへの船出をけん引
4年時には秋季関東大学リーグの入替戦で、国士舘大にフルセットの末に勝って1部に復帰。4年を通じて、自身の中ではある程度の達成感を持っていた。アスリートの就職支援エージェントに登録して就職活動をしており、最終的には無事に内定も獲得。社会人としての第一歩を踏み出す。
――はずだった。
入社まで2カ月を切った、2019年2月。
知らない番号から電話がかかる。
篠崎監督からの、最初のラブコール。一度専修大の練習を視察に来たことがあり「顔は知っている」程度の間柄だったという。当然、就職が内定しているので断りを入れる。
しかし篠崎監督は諦めない。
かかってきた電話は1度や2度ではなかった。
「どうにか入団してほしい」
「地元出身だし、帰ってこないか」
「色々とやってほしいことがある」
期待されていることはひしひしと伝わった。
「何度も断ったのに、本当にしつこくて…」と笑いながら当時を振り返る酒井。最終的には家庭の事情も考慮しながら地元に戻るよう翻意した。

当時のガロンズは、現在にもまして発展途上。地域に密着したチームで、手作りと手探りの端緒についたばかりだった。コート内での成績も振るわず、1シーズンを通して自身が感じたのは「練習量の不足」だった。
自分の手で、一から作り上げる。
仲間を鼓舞して、課題を見つけて、成長する。
それは、中学時代と同じ状況だった。
実戦で出た課題を潰して強くなる方法しか知らない。2020-21シーズンに主将を任されると、篠崎監督に働きかけてひたすら練習試合を組んでもらった。そして課題を克服。毎週、それを繰り返す。
しかし中学時代と違うのは、チームメイトも社会人として働きながら練習をこなしていくこと。バレーだけに打ち込める状況ではない。シチュエーションはシビアでもあった。
だがやはり、練習は嘘をつかない。
V2最下位だった前シーズンから6位まで成績を伸ばし、自身は個人成績で得点ランキング3位。学生時代とは違ってそれぞれ仕事があるものの、酒井が持ち続けてきたフィロソフィーは結果に結び付く。それを実感できた瞬間でもあった。

そして2024年、再び長野の地に降り立つ。引退を翻意しての入団。やる以上は中途半端にしたくないし、仲間に認めてもらわなければいけない。再び主将も任された。
新生Vリーグの中で、格上に挑んでいく。
北海道での経験を生かして、チームを牽引する。
そして臥竜の里に芽吹いたバレーの熱を、大きなうねりに変えていく。
「ガロンズは前から地元に受け入れられていたと思うけど、選手の規律も取れて振る舞いもしっかりしている。何より着実に力を付けている。そこに自分が戻ってきて果たすべき役割は、学んできたことを全て伝えて結果を出すこと」
「強くなるのはもちろんだけど、もっと応援してもらえるようにならなければいけない。強くなっていい試合をすれば面白いと感じてもらえると思うし、エンターテイメント性が生まれる」
「この好循環が、『チームを応援したい』という気持ちに繋がる。もっと応援されるチームになってほしい」

チームとしても個人としても、目指すべき高みは同じ。将来的なSVリーグへの参入。今季もリーグ改編でV参戦を果たしており、従来よりも格上との対戦が増える。厳しいシーズンが待っているのは間違いないだろう。
しかしそれを、酒井は「チャンス」と捉える。
負けても、くじけても、また立ち上がればいいだけだ。そこには成長につながる数々のヒントが散りばめられている。
「失敗したら次は勝てばいい。どれだけ負けても、最後に勝てばいいんで」
涼しい顔で、さらりとそう話す酒井。価値観が練り上げられた故郷で、最後に笑う時が来た。

PROFILE
酒井 駿(さかい・しゅん) 1997年3月4日生まれ、長野市出身。小学3年生の時にバレーボールを始める。裾花中ではセッターを務め、主将だった3年時には全国中学大会で8強入りを果たした。高校は東山(京都)でプレーし、3年時は主将。専修大4年時にセッターからアウトサイドヒッター(OH)に転向し、秋季関東大学リーグで入替戦を制して1部復帰した。卒業後は長野GaRonsに加入。2年目の2020-21シーズンは主将を任され、チームもV2で6位。21-22からの3シーズンはヴォレアス北海道に在籍し、V1も経験した。182cm、77kg。
LINE友だち登録で
新着記事をいち早くチェック!
会員登録して
お気に入りチームをもっと見やすく